前回までのあらすじ
主人公は、正木由羅(まさき ゆら)。40歳、既婚、5歳の息子を持つワーキングマザー。
彼女は自身に課す”美徳”というものに従い、仕事でも家庭でも模範的な人物を目指すべく日々を過ごしている。しかし、それが故に、自己肯定感との葛藤に対峙することもしばしば。例えば、一回りほど年下の高橋に対し、3年以上も教育を担当するも手応えを感じられずにいた。
そのような中、ある日突然、上司の水田に呼び出され、異動の内示を受ける。
異動先はどこなのか。その先に迫る。
風神と雷神が描かれる巨大な壁画を覆うガラス窓に、ゆったりと滑るように雲が流れている。
黒のプリーツスカートから伸びる2本の脚の先端は温かい。足元から湯気が立ち昇り、それは雲のようにも見える。
由羅は大理石に囲まれた美術館のその場所で、森山成美を待っていた。
それは、数日前に会った梶泰介からの指示だった。
*
「い、異動ですか…? この時期に、ですか…?」
「発令日は12月1日。いや、確かに珍しい時期なんだけどね、深い意味はないよ。10月の定期異動の時期ズレのようなものでね。」
水田は椅子に深く腰掛け、両手をひじ掛けに置きながら言った。中年層の恰幅の良い体を包むグレーのスーツは少しくたびれている。
「そ、そうですか…。」
深い意味はない、と言われると、それはそれで釈然としない。ただでさえ、心の準備のない中での内示である。とりとめのない返答をするしかなかった。
対面に座る水田との間には、長細い会議デスクが両者の空間を遮断するように横たわっている。普段の打ち合わせでは、各自がノートパソコンを開きつつ会話が繰り広げられるが、今日のように机上に何も置かれていないそれは、得体の知れないのっぺりとしたものに見えた。
「あの高橋がなんとか成長したのは、正木君のお陰だ。このタイミングでヤツの教育係としての役割をひと段落させて、正木君が更にキャリアアップする機会になればと思っているよ。」
”キャリアアップ”という言葉を押し付けられたような気がした途端、ぞくっと悪寒がした。
そんなものは、とっくに諦めていたからだ。
*
18年前、由羅が大学を卒業し、初めて就職した会社は、食料品小売業界の会社だった。都内の高所得者向けの高級品目を取り扱うスーパーマーケットが主な事業であり、その店舗の一つである駒澤公園店が、当時新卒だった由羅の初めての配属先だった。
そこで3年間の現場経験を積んだ後、本社広報部へ異動となり、社外からの取材依頼などの調整役を担当することになった。
後に夫となる太一は、同じく広報部に在籍していた2学年上の先輩だった。甲斐甲斐しく由羅に本社業務のイロハを教えてくれる太一に対して、次第に好意を寄せるようになった。太一も由羅に好意を寄せていたのだ。お互いに新卒入社という共通点もあり、二人はごく自然な流れで付き合うようになった。
太一は仕事の手際が良い男だった。そんな太一を横目にしていると、自分が鈍臭く思えて、時折惨めな気持ちになるのだった。ある時、由羅は太一に対する密かな嫉妬心が少しずつ芽生え始めていることに気が付いた。そして、異動から3年ほど経った頃、今いる小さな出版会社に転職することを決断したのだった。
内定をもらうまでは、太一に相談することはなかった。転職活動することが、新卒で入った会社に対してのちょっとした裏切り行為にも思えたし、何より太一がいない職場のほうがマイペースでいられると考えたからだった。
それは、約半年後に控える結婚というイベントが控えていたことも要因の一つだった。身内が社内にいることが、由羅にとっては何故だか落ち着かないことのように思えたのだ。(しかし、太一は程なくして別部署へ異動し、現在はバイヤーとして勤務している。)
その後、転職してからも広報業務にしばらく当たっていたが、由太を出産して復帰後に配属されたのは総務部だった。それは由羅にとって未経験の分野だった。
そもそも社員120名ほどの会社において、育児休業を取得するのは6年前の当時はそれなりに勇気のいることだった。そのため、職場復帰できるだけでもありがたいと思い、雑多極まりない業務を恩返しのつもりで必死にこなしてきた。
それにしても、総務部の業務は限りなく”何でも屋”だった。連日のように目まぐるしく入る対応事項に直面すると、次第にキャリアとして自分が積み上げているものが分からなくなっていった。
それでも由羅を突き動かす原動力は、己の美徳に適っているか、ということだけだった。キャリア志向を考え始めると、自分が苦しむだけとわかっていたのだ。
そもそもキャリアアップという水田の言葉は、ていの良い常套文句だと分かっていた。おまけに水田に労われるほど高橋の成長を感じられないことも相まって、釈然としない気持ちがますます大きく膨らみ始めるのだった。
すると、水田が再び小さく咳払いをした。ここからが本題、といった雰囲気を瞬時に感じ取る。
「それでだな、異動先の上司は、梶さんだ。」
その名を聞いた瞬間、由羅の思考が硬直した。
「梶さんのアシスタントが今後の職務になる。広報時代のスキルに加えて、総務での色々な業務経験が活かせると思うよ。」
「梶さんって…、あの梶泰介さんですか?」
自然と梶のフルネームがついて出る。
「他にどの梶さんがいるんだよ。そう、執行役員の梶さんだ。ちょっと変わり者で有名だけど、まぁ、色々と勉強になると思うよ。」
取締役会や株主総会に関わる業務もこなしている由羅だけに、わざわざ梶が誰かを再確認してきたことに水田は一笑する。どうやら状況を理解できずにいるであろう由羅に対し、説明を付け加えるべくデスクに身を乗り出した。
「梶さんはこれまで社外取締役だったが、今年から執行役員に就任して、正式にうちの人になっただろ。アート分野に精通してるってことで、その担当役員としてね。うちのライフスタイル誌にアート要素を強化させるっていうのは正木君も知っての通りだと思うんだけどさ。」
水田の言葉を慎重に聞き入れるように、デスクの一点を見つめながら静かに頷く。
「それでだな、これも、君がよく知っている通りだけど、梶さんは滅多にこっちに顔を出さない。自宅は都内のどこからしいんだが、日中は別宅がある鎌倉で大抵過ごしていて、彼とのやりとりは殆どリモートだ。一匹狼みたいなもんだから、それで事足りてるんだけどさ。」
「それでは、私の出社する先は…?」
由羅は俯き加減だった顔を上げ、水田に尋ねた。
「アシスタントが欲しいってオーダーは梶さんからなんだ。軌道に乗ってきたんだかわからんが、細かいことは聞いてなくてな。挨拶がてら、諸々直接聞いてみてくれないか。」
膨張していた釈然としない気持ちに小さな穴が空き、すぅっと萎んでいくような感覚がした。
ー かじ たいすけ…
由羅は、梶の名を記憶の空間の中で読み上げ、その音を反響させた。梶を一度だけ取締役会の日に見かけた記憶を静かに呼び起こすために。
梶とは、どのような男なのか。由羅の記憶の中を探る。
次のページへ
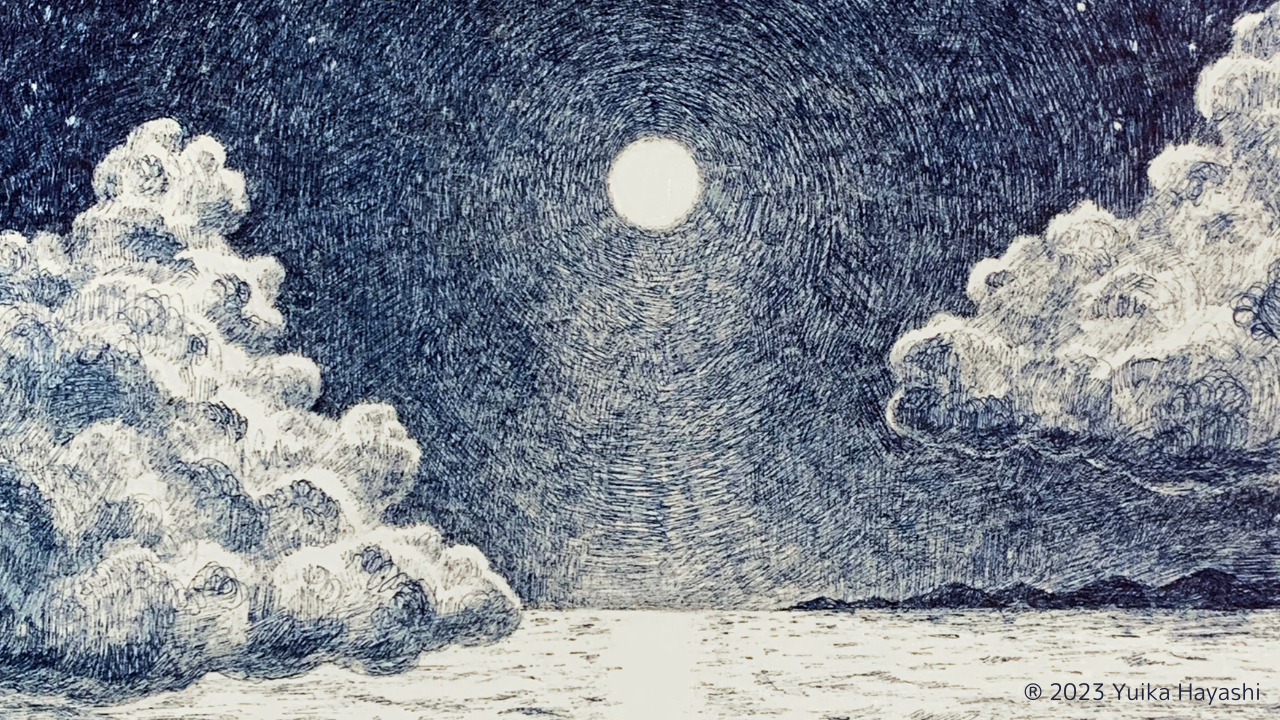
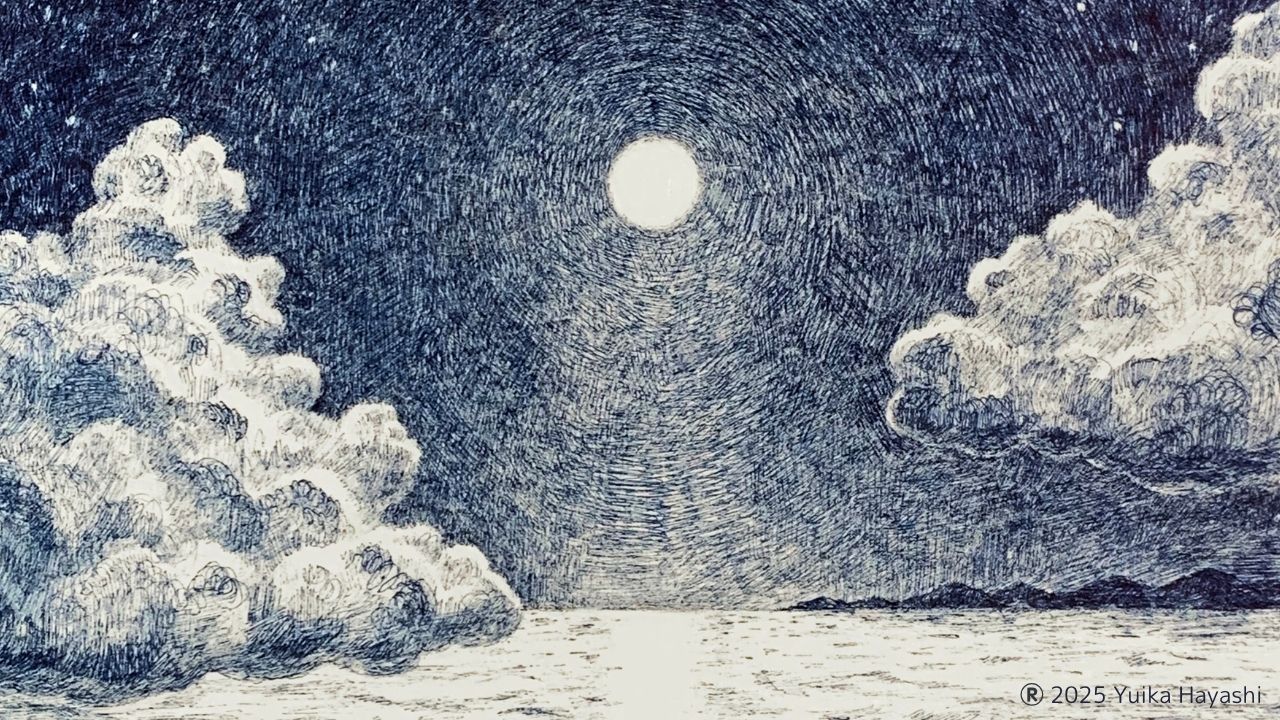
コメント