
「ふぅん、今夜のライブも楽しそうだ。」
「ブルー… ノート…?」
エントランスに掲げられているボードに視線をやる梶の横で、由羅が ”Blue Note” の文字をゆっくり読み上げた。
「うん。元はニューヨークの名門ジャズクラブなんだ。毎晩生演奏が楽しめるよ。いまやジャズだけじゃなく、色々なジャンルの音楽もね。」
そこは根津美術館からさほど遠くない場所だった。キリリとした青いネオンと対比するような温かなぬくもりある明かりの狭間に、黒々とした重厚なドアがどっしりとエントランスに構えている。
その扉を開けば中は特別な空間であることは、実際に入らずとも容易に想像できた。
しかし物理的に近くにあるのに、まるで人ごとのように心の距離を感じてしまう。由羅には音楽を聞きにわざわざ足を運ぶことが、どうも非現実的に思えてしまうのだ。
いつの日かあの重そうな扉に手をついて奥に入ることはあるのだろうか、いや、あるまい、などと、建物の横を通り過ぎながら、意味もなく自問自答する。
「さぁ、もうすぐだ。」
ブルーノートからほのかに漂う音のような匂いのような不思議な余韻が混じり合う空間のうちに、梶がひっそりと存在する路地を緩やかに左折した。
路地に入るとすぐに左手に小さなセレクトショップがあった。暗がりの道にささやかな明かりを灯している。その先は100メートルもしないうちに行き止まりになっているようだ。
ー こんな路地裏にバーが…?
由羅が疑いながら奥の方へと足を進める。
するとしばらくしないうちに、アイビーがびっしりと蔓延る巨大なコンクリートの塊が突如眼前を支配した。
その姿はまるで都会の喧騒の中で闇闇と静かに眠るケモノのようだ。
音はないのに、音を感じる。聞こえないケモノの心拍や寝息の音が。由羅が息を呑む。
「すごい量の蔦ですね…」
「うん、雰囲気あるよね。好きなんだ。」
好きなんだ、という言葉がひどく懐かしく響いた。
ー 好き ー
最近あまり使ったことがないように思える。
”嫌い” という言葉すらも。
梶はごく慣れた雰囲気で外階段を登っていく。上がっていく梶の後ろ姿を見上げつつ、アイビーの合間から漏れる窓の明かりの様子を伺うと、どうやらこの建物は3階建てらしいことが見て取れた。
外階段は夥しい青々とした葉が這う壁にぴたりと張り付くように存在していた。一段一段上がる度、巨大なケモノの背中を這って上がっていくようで、不思議に神聖な気持ちが身体を満たしていく。
一番上まで登り切ると、奥の方に木製のドアが照明によってぼんやりと浮かび上がっている。ドア前の通路には膝下の高さほどの小さな黒い看板が立てかけてあって、その真ん中に、
BACKSIDE BAR
と表記されていた。
真鍮製のハンドルを引いて梶がドアを開いた瞬間、ジャズの優しい音色が流れ出て由羅の耳元にすっと沁み入った。梶がドアを押さえると、由羅を先に店の中へと促した。
誘導に従い入り口を入るとすぐに小さなバーカウンターが姿を現した。カウンター奥の間接照明が、棚に所狭しと並ぶリキュールやウィスキーなどの瓶をゆらゆらと照らしている。
店内は全体的に木材が基調となっているらしい。明かりは必要最低限の間接照明だけしか施されていないためひどく暗いが、木のぬくもりのおかげなのか落ち着く空間が演出されていた。
バーカウンターは席数が4つほどで、店の奥のほうに4人がけほどのボックスシートが配置されている小さな店だ。その時分には、どうやら自分たち以外の客はいないようだった。
店内を見まわした際、由羅が目を奪われたのは壁際の棚にびっしりと納められた無数のレコードだった。
棚の下段にはレコードプレーヤーが置いてあり、LPレコードが規則正しく回っている。どうやら一番上段の棚に設置された2台のスピーカーに接続されているようで、ジャズはそこから流れていた。

レコードの棚に圧倒されていた由羅の背後で、こんばんわ、と女性の声が微かに聞こえた。声の主は成美だと一瞬でわかった。
後ろを振り返ると、梶と成美がカウンター近くで挨拶のごとく抱擁し合っている。
どこに視線をやったら良いかわからず少しばかり戸惑う自分のことを由羅は情けなく感じた。海外では普通のことだし、それに成美はかつてイギリスに住んでいたらしいではないか。
それにしても、今夜の成美はフルメイクが施されていて、日中の快活な姿とは別人のように妖艶だった。ノースリーブのスキニーなブラックタートルは丈が短く、くびれたウエストは生肌が露出している。
抱擁の後に梶の腕が成美の背中から腰にたどり着いた瞬間、由羅の頭の中が突如真っ白になった。
なぜなら二人は唇を重ねていたからだ。
いよいよ視線をどこにやったら良いかわからず、真っ先に下の方に移すと、成美の腹部が視界に入った。
その美しいへその下には、小さなドラゴンのタトゥーが描かれていた。
続き▶︎ 第13夜 | モーセとローストビーフ
この物語はフィクションであり、実在の団体とは一切関係ありません。
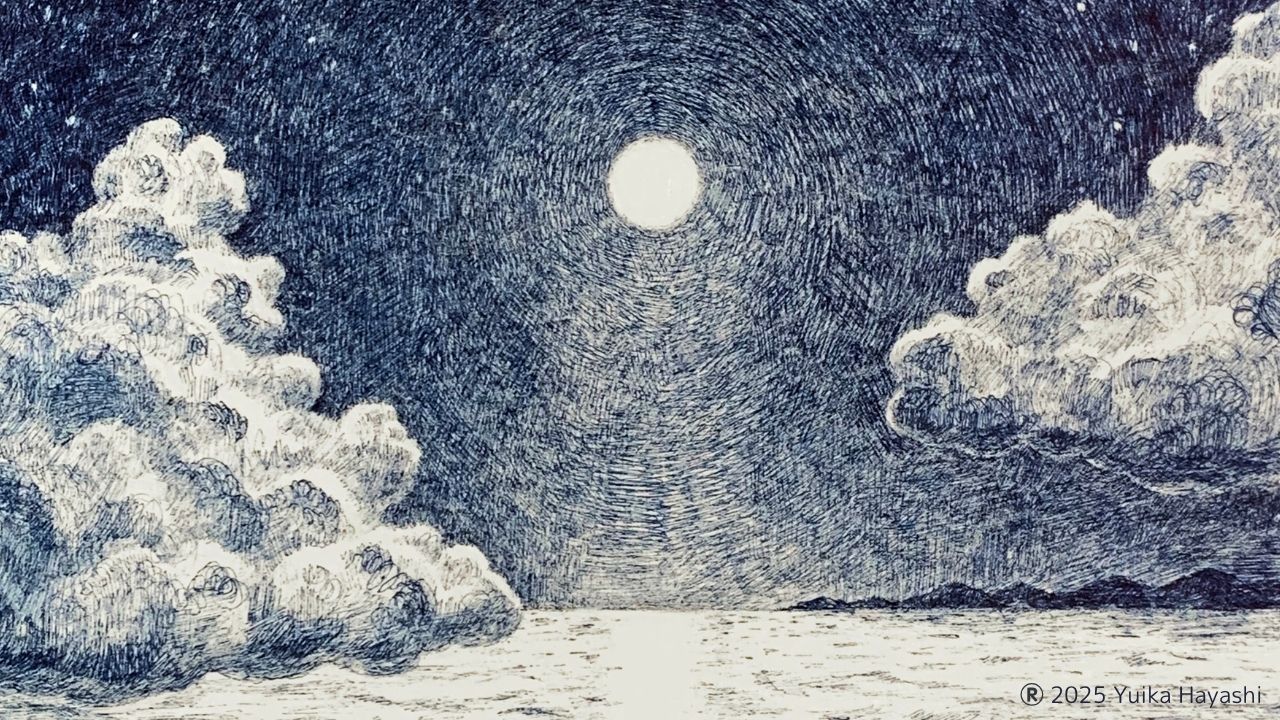
コメント