表参道交差点を背にして、みゆき通りを由羅は梶と並んで歩いていた。こぢんまりとした通りは、表参道を歩く時よりも梶との距離が近くに感じられる。
由羅は、これまでバーといった所に殆ど行ったことがないことだとか、夜遊びすることも子供が生まれてからほとんどないだとか、この辺りは随分久々に来たことだとか、そんなことを右隣に歩く梶にペラペラと話した。まるで舌が踊り出したかのように。
もっとも梶は静かに耳を傾け、ふぅん、とか、へぇ、とか、相槌を打つだけだった。
冷静な梶に対して、由羅は自分がまるで幼児が大人に話を聞いて聞いてとばかりに話すさまを滑稽に思った。明らかに浮かれている自分のことを。
およそ10年ぶりに歩く南青山は、想像していたよりも変わらない風景が広がっている。都内のターミナル駅界隈は再開発が進み、わずか2-3年もしないうちに雰囲気ががらりと変わっていくというのに。
以前から相も変わらずみゆき通りの入り口付近に鎮座するコム デ ギャルソンの旗艦店が右手に見えてきた時、かつて参列した友人の結婚式がこの通りを一本奥に入ったレストランウェディングだったことを思い出す。
その日も冬の厳しい時期だった。薄手のドレスの上にコートで身を包むものの、冷たい風がストッキングを履いただけの足元に吹き付け、寒さで凍える自分のことが妙に惨めに思えた。
あの頃は30歳に差し掛かる頃だった。今よりも若さとか気力とか女として色々なものを持っていたはずなのに、些細な物事の破片に触れる度、いとも簡単に心に傷がついた。小さな傷がいくつもいくつも。
レストランウェディングと凍える足元。
南青山のハイブランドとちっぽけな薄いドレス。
そういった小さな破片たちに傷つけられた心は、今や痛みを感じにくくなっている。
更に先に進むと、プラダビルの外観が見えてきた。
建築の表層が構造体と一体化された菱形格子から数百枚にもおよぶガラスが膨らみを帯びて張り出している。その姿は大きな宝石のように夜の通りに煌めきを与えていて、思わず足が止まってしまうほどだった。
ビルを見上げ、由羅が、綺麗… と小さく呟くと、
「正木さん、コンタクトレンズしてる?」
と、これまで由羅の話を聞いては頷いているだけの梶が口を開いた。
なぜそんなことをと不思議に思いながらも、していることを伝えると、
「このガラスは外郭だけでね、ちょうどコンタクトレンズを瞳の上に乗せている状態に似ているんだ。」と梶は説明した。
「そうなんですか…」
「どの角度からでもこのビルの内部を見通すことができるだけでなく、視覚的な作用を活用して焦点を合わせている。つまり、見てほしいものに焦点を合わせるようにできているんだ。」
「”見てほしいものに焦点を合わせる”… ですか。このビルは見た目だけではなくって、機能美も持ち合わせてるんですね。」
「うん、確かにそうだね。」
梶は新しい解釈を味わうかのごとく呟いた。
やっぱり不思議な空気を纏った人だ。由羅は梶の横顔を見ながら思う。
「あ、ヨックモック…」
青いタイルの外観が象徴的なヨックモック本店の横を通り過ぎようとした時、かつて母とこの街を歩いたことが突然思い起こされた。由羅が中高校生のころ、たまの休みに連れて来られたのだった。
由羅の母は常々「結婚したら、本当は都会に住んでみたかったの」と言っていた。平凡な郊外での生活に飽きてくると、週末に由羅とひとつ下の妹も連れ立って都心へと電車を乗り継ぎ向かった。
南青山に来る時は決まって、「ここはちょっとした外国風情が味わえるからいいのよ」と話しながら散策を楽しんでいた。ハイブランドのブティックにも臆することなく入店したり、ある時は青山霊園へ行って偉人の墓を見せては歴史のことを教えてくれたりもした。
そして、帰りがけには決まってヨックモックでシガールを買うのだった。ヨックモックのお菓子を買って帰りましょう。おばあちゃんへのお土産よ、と言いながら。
由羅がそんな昔話を何と無しに話すと、梶は、
「へぇ。君のレンズ、良い思い出に焦点を合わせたようだね。」
と言って、思いがけずその顔に優しい笑みを浮かべたのだった。
梶が見せる柔和な表情にドキリとした。そしてレンズの比喩はプラダビルの前で話したことだと少し遅れて気付く。
「私の潜在意識が、その思い出を”見てほしいと焦点を合わせた”のかもしれませんね。」
由羅も笑顔で答えると、梶は「ちょっと待ってて」と一言残して、閉店間際のヨックモックへ颯爽と入っていってしまった。
またも予測できない梶の行動に、由羅が慌ててガラス張りの外壁から店内を覗いてみると、何やら会計している様子が伺える。
ー 急に何を買っているのかしら…
会計を終えたであろう梶が早々に店から出ると、ヨックモックの紙袋を右手にぶら下げている。
「はい。シガール。」
紙袋を由羅に差し出しながら梶が言った。
ー え…?
戸惑いながらも、つい受け取ってしまった紙袋の中を覗いてみると、クリスマス限定缶のシガール詰め合わせが入っていた。
続き▶︎ 第12夜 | BACKSIDE BARと小さなドラゴン
この物語はフィクションであり、実在の団体とは一切関係ありません。
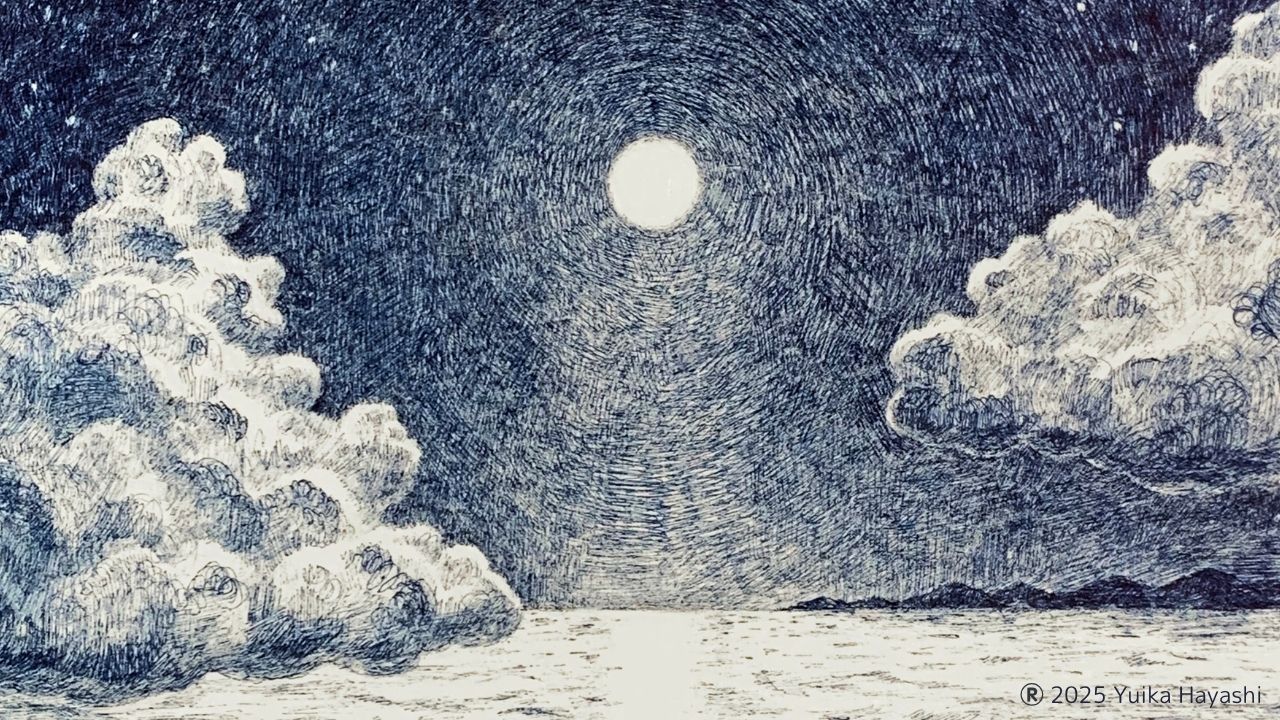
コメント