ねぇ、20年前の若かりし日の私。
今の私を見てどう思う?
幸せそうに見える?
*
由羅はほんの数時間前に見ていたそんな夢のことも忘れて、駅に向かってひたすら走っていた。20年前から続いている習慣に、身も心も従順に反応してしまう。それは、定時よりも余裕をもった出社を心がける、という習慣。
残業することが難しい彼女のメールボックスには、前日の退社後に届くメールが多く溜まっている。
だからこそ出社する人が少ない静かなオフィスで、ひとまずメールチェックすること。
そして定時が訪れる頃にはメールをさばききり、同僚にタイムラグを感じさせないようにすること。
それが彼女にとっての美徳なのだ。
彼女の美徳は、それ以外にもたくさんある。
例えば、気配り上手でいること。
例えば、負の感情を表に出さないこと。
例えば、謙虚で控えめでいること。
例えば、約束は絶対に守ること。
例えば、人に決して迷惑をかけないこと。
例えば、仕事では子供を理由にしないこと。
そして…
例えば、不貞行為は絶対にしないこと。
秋も深まって年末の足音が聞こえてくる時期だが、駅に着く頃には首元のストールに湿り気を感じていた。ホームの列の最後尾に立ち、電車遅延のないことに安堵すると、保育園で過ごしている我が子のことを想った。
この朝、5歳になったばかりの由太が久々におねしょをした。
それは小さなペットボトルの量くらいに思われた。ごく当たり前のようにベッドマットをするりと通り超え、マットレスまで水分が侵入している。寒さが本格化してきたからと、日曜日におろしたばかりのかけ布団を恐る恐る触ってみると、少し濡れている感触がした。
家を出るまでに残された時間はおおよそ1時間。昨夜深い時間に帰宅したであろう太一の大きなイビキが、隣の部屋から鳴り響いている。そんな夫を無理やり起こしたところで、出かけるまでに寝室の惨状を回復することは難しいことを察する。
「由太。珍しいね。どうかした?」
「うん…、わかんない。」
眠い目を不器用な手つきでこすりながら、ぽつりと静かに答える由太。
どのような回答を期待して質問したのだろうと、由羅は思った。
ー 何か悩みがあるとか、何か心配してとか。
そういうことなら納得するとでも思ったの?
由太の寝癖が視界に入る。髪を切ってやれていないことに、”改めて”胸がチクリとする。
時間がないという理由で散髪を先延ばしにしているが、耳が髪ですっかり隠れてしまった息子の姿を見るたび、日に日に自己肯定感が下がるような気持ちがした。
5年前に”母”というものになった途端、自分と子供の存在の境目がわからないような感覚になった。
散髪やおねしょの惨状をなんとかすること。そんな些細なことまでもが、自分の抱える人生の課題であると大きく捉えてしまうのだった。
小さなつむじの近くで跳ねる髪を撫でながら、なんて柔らかくて美しい髪だろうと思う。油断すると泣きそうになる気持ちを抑えて、由太をリビングへとうながす。
寒々とした風呂場で熱々のシャワーを全開にする。みるみる湯気が立ちこめ、由羅の眼鏡が曇った。
風呂場の中が湯気で充満し始めたところで、眼鏡を脱衣所の洗濯機の上に置きつつ、由太を呼んだ。
「ゆうちゃーん!早くこっちに来て、パジャマ脱いでー!」
*
ー 帰ったら、一気に洗濯しなきゃ….
会社だけでなく自宅でのタスクが増えたことに悲しみを覚えつつ、ホームに入る電車の姿を確認すると、バッグからマスクを袋から開封して取り出し、付けた。
すると、途端に眼鏡が曇った。今朝の風呂場の時のように。
*
「正木さん、今日はメガネなんすね!」
オフィスに着くやいなや高橋から眼鏡を指摘される。
「あ、うん。今朝ちょっとバタついてたからコンタクトできなかったの。ていうか、高橋くん、まずは、おはようございますでしょ、普通。」
フレッシュマンと思っていた高橋はあと半年もせずに入社4年目となるが、未だに言動が学生の雰囲気だ。長身でほっそりとした体つきに加え、面長から見せる表情はあどけない。
由羅は高橋の入社当初から彼の教育係としてやってきたが、どうやら人には生まれ持った素質というのがあるらしく、隣に座る若者の成長を期待したほど感じることができないでいる。どんな状況であろうと顔を歪めることもなく飄々としているせいだろうか、指導が高橋の体に染み込んでいく様子がうかがえないのだ。
「すみません….。正木さんの到着が定時ギリギリだし、メガネだし、めずらしいなって思ったんです。」
高橋は挨拶をしなかったことをいつもの調子で表面上侘びつつも、いたって純粋な気持ちで返答した。
ー まぁ、確かに…。私にしては、確かに珍しいわよ…。
珍しいことを知っているということは、普段の由羅のことを知っているということだ。そのことが何か特別なことのように感じ、心の中で小さい火が灯るような感情に気が付く。慌ててそれを打ち消すように、
「息子がおねしょしたのよ。」
と答えると、高橋は、
「え?おねしょ?息子さんっていくつっすか?」
と驚いたように言った。
「5歳になったばかりよ。このところ全然おねしょなんかしなかったのに。」
「あ、正木さんのお子さん、そんなに小さいんでしたっけ!つか、5歳の子供っておねしょすること珍しいんですか?自分の時、どんなだったか覚えてないなぁ…」
そう答えるやいなや、由羅に向けていた顔をノートパソコンの方に向き直し、さもこの会話は終了と言わんばかりの空気を漂わせた。
由羅は、その数秒前に一瞬でも浮かれた気持ちになった己を恥じた。
ー バカみたい。高橋くんが私の何を知っているというのよ。
26歳の男にとっては、40代の女とはティーンエージャーの子供がいるようなイメージなのかもしれない。そもそも一回り以上も若い男が自分に関心を持つこと自体、あり得ないのだ。
そんなことを思うと突如悔しくなった。
由太は今日に至るまで、突然の発熱などの体調不良に多く見舞われてきた。免疫機能が未発達の幼児にはよくあることだ。しかし由羅の美徳として、子供が原因で同僚に迷惑をかけることを嫌った。
そういった日には決まって由太を自宅で看護しながら、リモートワークをするのだった。無論、病児が側にいては思うように仕事が捗らない。その分、密かに夜な夜なパソコンの電源を入れ直すことも多々あった。
当時、新入社員だった高橋の指導役に指名された時、由太は2歳だった。先輩としてしっかりした姿を見せることも由羅の美徳だった。だからこそだった。
しかし、その苦労を3年以上も己の隣に座る若者は知らない。
次第に悔しさは、おかしみにも悲しみにも思えてきた。それはまるで、人を豊かな眠りへと誘うための寝具が、子供の排泄物に濡れてしまった姿と重なった。
*
「正木くん、ちょっと…。」
その日の昼近く、背後から低く太い声がした。振り返ると恰幅の良い水田の姿があった。ごつごつとした指は会議室の方を指している。由羅が何かを答える前に、無言で水田はそこに向かっていった。
ー 水田部長から呼び出しだなんて。何かしら…。
通常の指示事項ではないと察した。
ー まさか、何かミスでも起こしたのかしら…
仕事に対して潔癖過ぎる由羅は、ミスを起こすことは自分にも周りにも信頼を損なうような気がして、とても毛嫌いしている。それだけに、そのような予感をすること自体が恐ろしいことのように感じた。
脈拍が上がり出したことを自覚したため、急いで一回だけ深呼吸をしてから、会議室に入室する。
先に着席していた水田が、対面に座るよう手を伸ばしている。
ドアを閉め、軽く一礼してから着席した途端、ノートパソコンを持ってくるのを忘れていたことに気が付き詫びる。慌てていたのだろう。
「いや、パソコンはなくて大丈夫。」
水田は答えると、小さく咳払いをした。そして、一呼吸置いてから、続けて言った。
「正木くんね、この時期にしちゃ珍しいんだけど、君に異動辞令が出た。」
続き▶︎ 第2夜 | 梶と成美
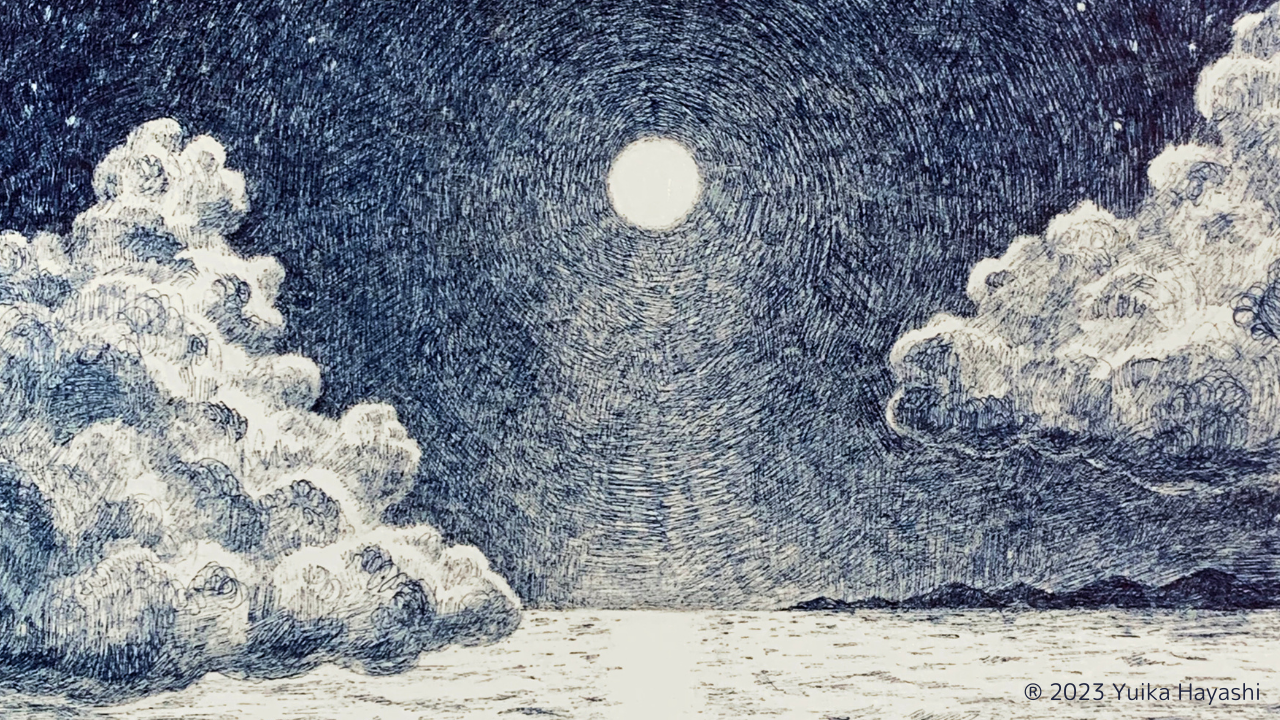
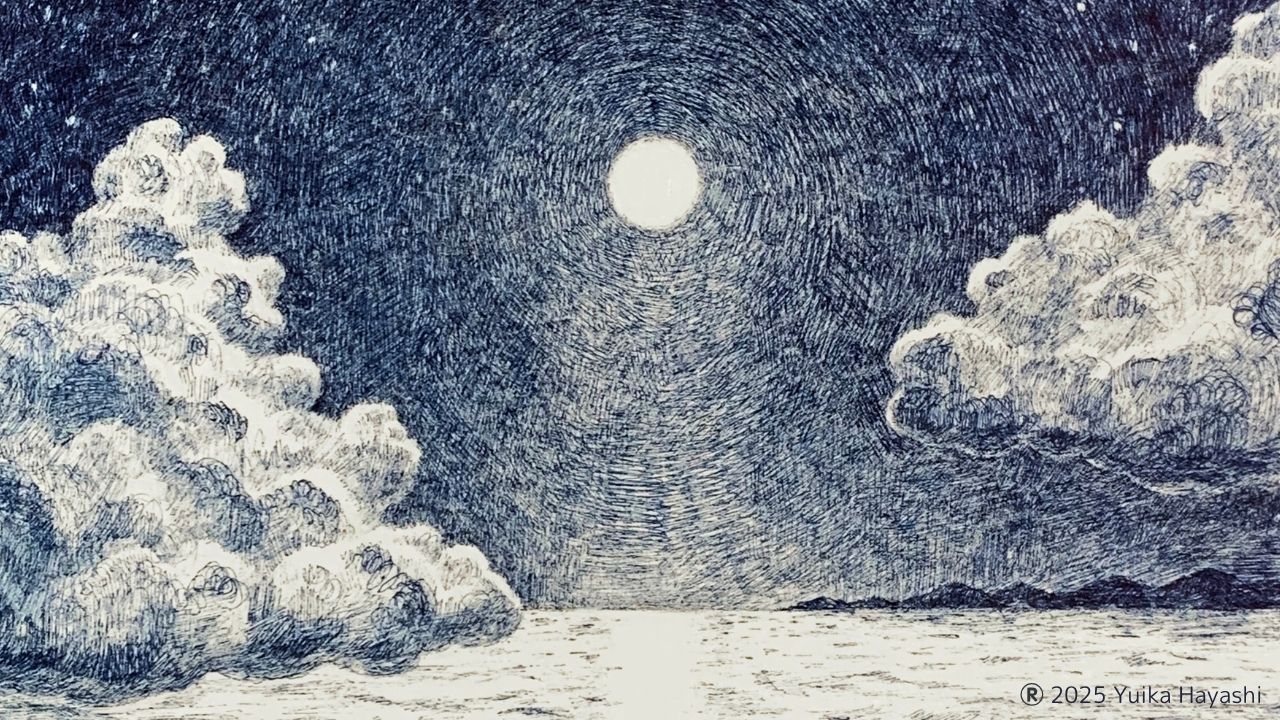
コメント
コメント一覧 (2件)
ついに始まりましたね!
由羅さんの気持ち、ちょっとわかるかもです・・・
転調のタイミングもよいですね~。続きが楽しみです!
蒼子さん、Nina初のコメント、ありがとうございます!
はい、とうとう始まりました…
由羅の気持ち、ちょっと分かりますか?
蒼子さんにも似たような一面があるのかしら…
これからも楽しんでいただけたら嬉しいです♡