澤村 塔子(以下「当社」といいます)は、当社が運営するウェブマガジン「Nina Novembre」(通称「ニナ・ノーヴァンブル」。以下「本サイト」といいます。)の会員規約(以下「本規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
当社が提供する会員向けサービス(以下「本サービス」といいます)の利用には、本規約に基づく会員登録が必要となりますので、会員登録にあたっては、必ず以下記載の本規約と別途当社が定める「サイトポリシー」及び「プライバシーポリシー」をご確認いただき、ご同意の上でお申込みください。
第1条 (会員)
1. 「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人をいいます。
2. 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。
3. 本規約は、全ての会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約です。
第2条 (登録)
1. 会員資格
本規約に同意の上、所定の入会申込みをされたお客様は、所定の登録手続完了後に会員としての資格を有します。会員登録手続は、会員となるご本人が行ってください。代理による登録や18歳未満の方の登録は認められません。なお、会員登録申請者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該会員登録申請を当社の判断により承認しない場合があります。この場合、当社は、当該会員登録申請者に対し、承認をしない理由を開示する義務を負いません。
(1) 会員登録申請者が過去に本規約の違反などにより本サービスの利用の停止、又は会員登録の抹消が行われている場合
(2) 会員登録された内容に虚偽の事項が含まれている場合
(3) 不正に他人の情報を用いて申請をした場合
(4) その他会員登録申請を承認することが不適当であると当社が判断する場合
2. 会員情報の入力
会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。会員情報の登録において、特殊記号・旧漢字・ローマ数字などはご使用になれません。これらの文字が登録された場合は当社にて変更致します。
3. お支払い
会員情報に入力したメールアドレス宛にPaypal決済用のリンクをお送りします。ご登録確認後、暦日10日間経過してもご決済がない場合は、登録申請をキャンセル扱いとしますので、ご注意ください。
4. パスワードの管理
① パスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。
② パスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人が責任をもって管理してください。
③パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等は全て会員の責任となります。
第3条 (変更)
1. 会員は、メールアドレスなど当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡するものとします。
2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご注意ください。
第4条 (退会)
会員が退会を希望する場合には、会員本人が退会手続きを行ってください。所定の退会手続の終了後に、退会となります。なお、お支払い済みの会員費を返金することはできませんのでご留意ください。
第5条 (会員資格の喪失及び賠償義務)
1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前に通知することなく、当社の判断により、会員による本サービスの利用の停止、又は会員登録の取り消しを行うことができるものとします。なお、この場合、当社の判断により、本サービスの利用により既に有効に成立している申込等についても取り消すことがあります。
(1) 過去に本規約違反などにより会員登録が抹消されていることが判明した場合
(2) 会員登録された内容に虚偽の事項が含まれていることが判明した場合
(3) 不正に他人の情報を用いて会員登録をしたことが判明した場合
(4) 本規約に違反した場合
(5) 第7条(禁止事項)に該当する行為を行った場合
(6) その他、反社会的勢力に該当する場合等会員として適切でないと当社が判断する場合
2. 会員は、前項各号に該当する場合、当社からの事前の通知を要することなく当然に、会員が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を失うものとし、直ちに債務全額を当社に弁済するものとします。
3. 第1項の定めにより、当社が会員に対して行った会員登録の取消、申込等の取消により会員に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
第6条 (会員情報の取扱い)
1. 当社は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社は会員情報を開示できるものとします。
(1) 法令に基づき開示を求められた場合
(2) 当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合
2. 会員情報につきましては、別途定める「プライバシーポリシー」に従い、当社が管理します。当社は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、及びサービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、当社において利用することができるものとします。
3. 当社は、会員に対して、メールマガジンその他の方法による情報提供(広告を含みます)を行うことができるものとします。会員が情報提供を希望しない場合は、当社所定の方法に従い、その旨を通知して頂ければ、情報提供を停止します。ただし、運営に必要な情報提供につきましては、会員の希望により停止をすることはできません。
第7条 (禁止事項)
本サービスの利用に際して、会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。
1. 法令または本規約並びにその他の規約等に違反すること
2. 当社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
3. 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
4. 虚偽の情報を入力すること
5. 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込むこと
6. 当社のサーバーその他のコンピューターに不正にアクセスすること
7. 会員ID及びパスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
8. その他当社が不適切と判断すること
第8条 (本サービス)
1.会員登録を行った会員は、本サービス利用料として会員費2,711円(税込)を当社の指定する方法でお支払いいただきます。
本サイトは、次のサービスから構成されます。なお、当社は、当社が必要と判断した場合、会員への通知を行うことなく随時会員向けの本サービスの内容の変更及び終了を行うことができます。
(1) 本サービスで提供されるすべてのコンテンツを閲覧することができます。
(2) 会員限定コミュニティサービスは、本サービスで提供される会員のみが参加することができます。なお、一部の当該サービスは、第8条に定める会員費の他、別途、追加料金が発生する場合があります。
第9条 (サービスの中断・停止等)
1. 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部または一部を事前の通知なく、停止することがあります。
(1) システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
(2) システムに負荷が集中した場合
(3) 火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合
(4) その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合
第10条 (サービスの変更・廃止)
当社は、その判断によりサービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。
第11条 (免責)
1. 通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サイト・サーバー・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しません。
3. 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条 (本規約の改定)
当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものとします。
第13条 (準拠法、管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合、当社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



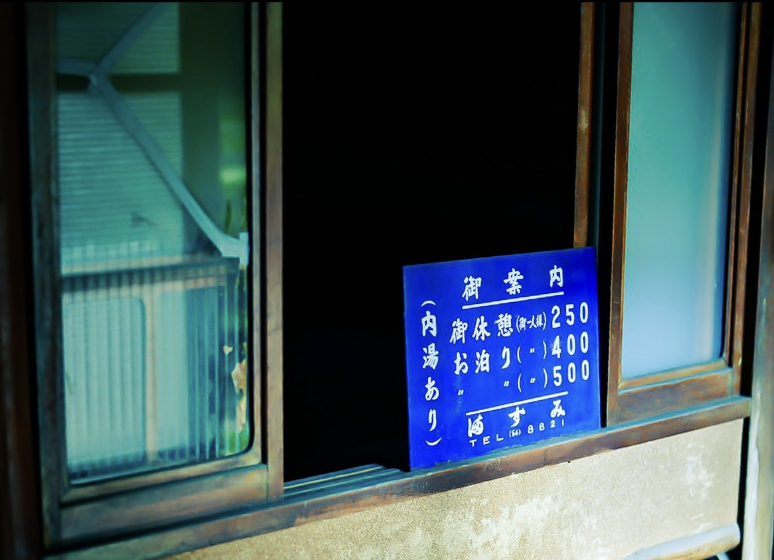

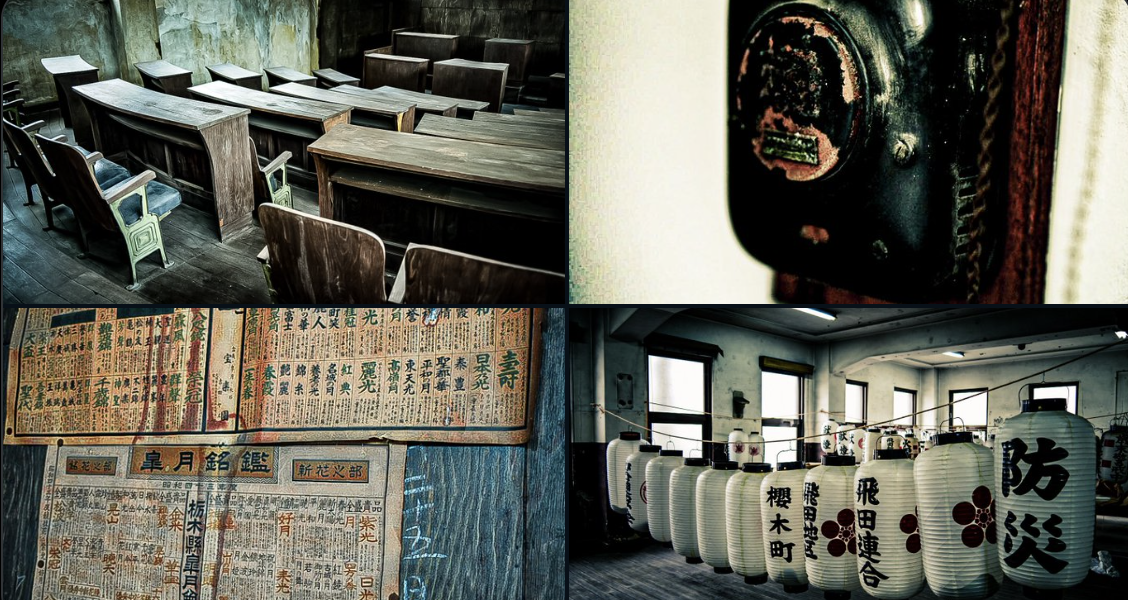






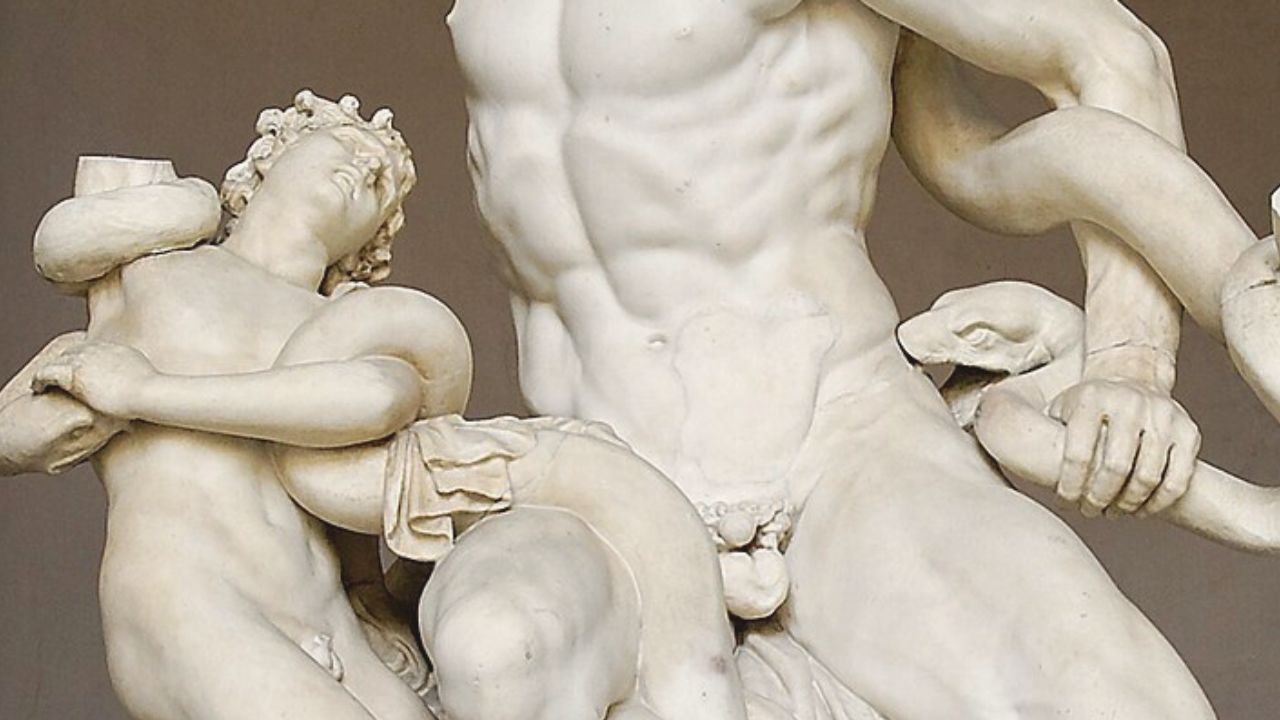
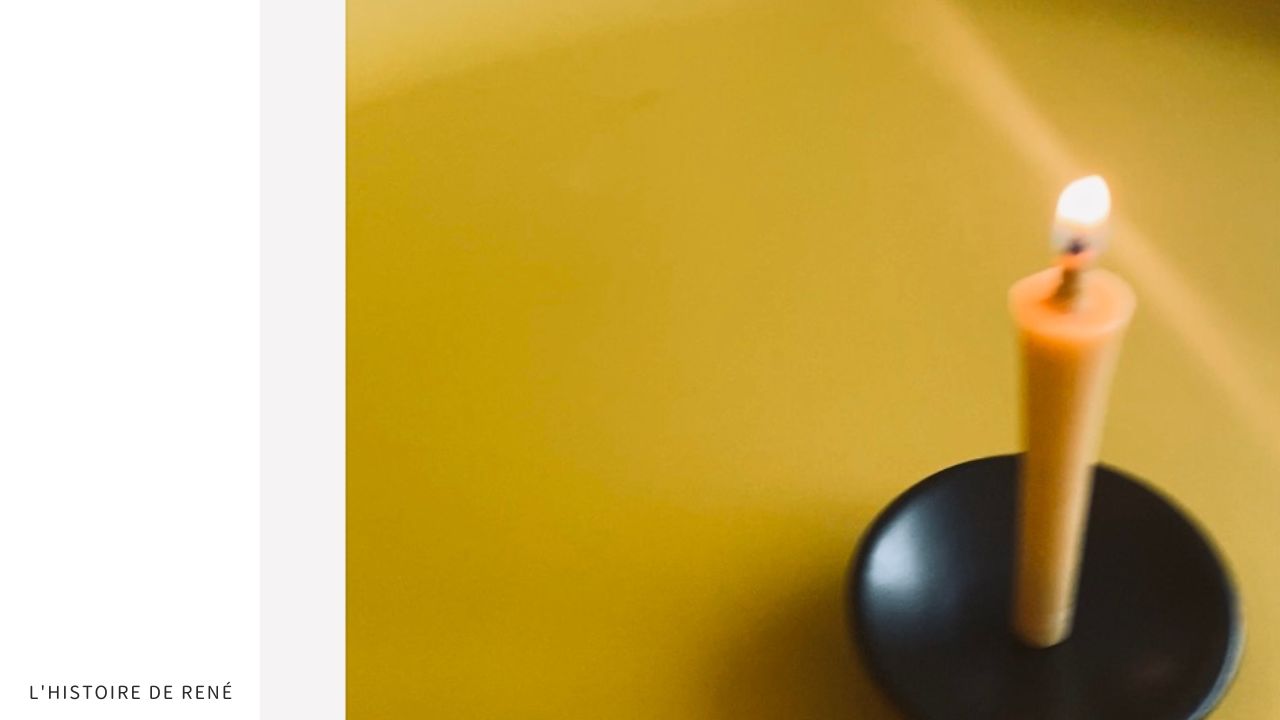

コメント